血便・下血ってどんな状態?
便に血が混じること(肛門から血が出ること)を血便と言います。多くの場合は痔による出血ですが、それ以外の原因として、食道から大腸までの消化管のどこかから出血していることが考えられます。通常、消化管の粘膜層には血管が通っておらず簡単に出血することはありません。そのため何らかの病気などが関係していることが考えられます。
血便がどこからの出血なのかは、出血の色でおよそ検討をつけることができます。胃や十二指腸からの出血の場合は、胃酸が血液に混ざり黒または暗紫色になります(下血)。一方、大腸からの出血は胃酸と混ざらないことや出血してからすぐに排出されるため、真っ赤な鮮血の色となります(鮮血便)。胃や十二指腸からの胃酸と混ざった出血が便に交じっているものを下血と言いますが、世間では血便≒下血として用いられていることも多く、どちらでも意味は通じます。
血便・下血の原因
血便や下血は、加齢に従って多くなる傾向があります。下血は、現在では肛門から血液が出る全ての事態を指した言葉として使われることが多くなっていますが、本来は胃や十二指腸など上部消化管からの出血を指しています。下血があった場合、成人では胃・十二指腸潰瘍、重症化した胃炎などの他、胃がんからの出血の可能性があります。
鮮鮮血便などを認める、大腸や肛門といった下部消化管からの出血の原因としては、虚血性大腸炎、大腸憩室出血などの他、大腸がんや大腸ポリープなど悪性・良性の腫瘍、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患、O157に代表される腸管出血性大腸菌などの細菌感染による大腸炎、痔出血などが考えられます。
血便・下血の症状
- 便に血が混じる
-
黒い便が出た
-
排便後、拭いたペーパーに血液が付着した
-
便秘と下痢を繰り返す
-
残便感がある
-
便に粘液が付着している
-
便が細くなった
-
腹痛がある
- 便器が真っ赤
血便・下血の色と量
お尻から血が出る場合で一番多いのは、肛門の直腸側にできる内痔核(いぼ痔)からの出血です。肛門周辺からの出血ですので、真っ赤な鮮血が混ざることが特徴的です。これは鮮血便と言い、直腸のポリープやがんによる出血でも、同様に起こります。大腸の途中で、便に血が混じった場合は暗赤色便となります。また大腸が、何らかの理由で粘膜に傷ついた場合、粘液に血が混じる粘血便となります。胃や十二指腸といった上部消化管からの出血の場合、胃酸と血液が混じることで、真っ黒から暗紫色でドロドロした黒色便(タール便)の状態になります。
出血が微量の場合、肉眼では分からないため、潜血便(顕微鏡的血便)と言います。
いずれの場合も必ず受診して、原因をしっかりと突き止めるようにしましょう。
当院では消化器内科、肛門外科を併設していますので、血便や下血に関する総合的な診療が可能です。お気軽にご相談ください。
下血による体の変化
 消化管から出血が起こっているため、少しずつ失血による貧血症状があらわれることがあります。
消化管から出血が起こっているため、少しずつ失血による貧血症状があらわれることがあります。
主な症状として、めまい、動悸・息切れ、立ち眩み、頭痛があります。
また、一度に大量の出血をした場合、出血性のショック状態となることもあります。意識レベルが低下して失神に至る危険性があるため、興奮状態になる、血圧が低下する、脈・呼吸等が異常に速くなるなどの症状があった場合は注意が必要です。
血便がある場合に考えられる大腸疾患
大腸ポリープ
直腸は、便を一時的に蓄積しておく働きがあるため、大腸ポリープの好発部位にもなります。この部分にポリープができると、硬い便に擦られて出血することがあります。ただし、肉眼で見えるような血便ではなく、いわゆる潜血便となることがほとんどです。大腸ポリープは、その他の自覚症状がほとんど無く発見しづらい上に、放置すると一定確率でがん化することが知られています。そのため、毎年の定期健診による便潜血検査が大切です。
大腸がん
大腸がんは、進行すると様々な症状があらわれてきますが、早期の状態では自覚症状があらわれることはほとんどありません。
がん細胞は非常に壊れやすいため、便が擦れる程度で微細な出血が起こることがあります。こうした症状は、大腸のどの部分にがんができているかによって異なります。
大腸の部分ごとの症状の現れ方
盲腸 ― 上行結腸 ― 横行結腸のがん
この部分では、小腸から栄養を吸収された食物残渣(口や胃などに残った食べ物のカス)がたっぷり水分を含んで送られ、これから水分が吸収されていく状態です。
そのため、出血などの症状があらわれにくく、気づかないうちに大きくなって体表からしこりとなって触れたり、出血によって貧血症状が起こったりして気づくことが多いです。この部分でも、がんが発症することがあります。
下行結腸 ― S状結腸 ― 直腸S状部 ― 直腸のがん
だんだん水分が吸収され、硬い便となっていきます。
特に、S状結腸から直腸にかけては便が一時的に蓄積されるため、刺激となることで、がんが好発しやすい部位となります。
ただし、早期にはほとんど自覚症状が無く、やや進行した後に便潜血を起こしたり、便通異常を起こしたりして気がつくことが多いです。
潰瘍性大腸炎
近年、比較的若い世代を中心に増えてきている病気で、指定難病にもなっています。自己免疫の異常によって大腸に連続的に炎症がおこり、びらん、潰瘍などで腸管に傷が生じます。特徴的な症状として、腹痛、下痢に伴う粘血便などがあります。
虚血性大腸炎
何らかの原因から、大腸に血液を届ける部分がうっ滞して大腸粘膜が虚血状態に陥ることによって、急激に大腸粘膜が炎症を起こし、びらん、潰瘍状態になる病気です。
急な腹痛とともに下痢が起こり、その後血便が出ます。
便秘気味で肥満状態の高齢女性に多く、便秘のために強くいきむことなどが原因の1つと考えられています。
通常は、絶食などによって腸を休ませることで自然に治癒することが多いのですが、時に虚血で薄くなってしまった部分で穿孔などが起こることもあるため、注意が必要です。
出血性大腸炎
O157などに代表される腸管出血性大腸菌や、ベロ毒素を出す志賀赤痢菌などへの感染、抗生剤(特にペニシリン系でみられることが多い)の使用などによって、大腸粘膜に急激な炎症が起こります。原因物質が体内に入り、しばらく潜伏した後に、突然の腹痛、下痢、水様便に血液が混じるなどの症状を起こすことが特徴です。
血便の検査
まずは問診で、出血の状態、その他の症状、経緯などについて詳しく伺います。
便は、その色や便の状態によって、どの部位からの出血であるかある程度の推定が可能です。推定される出血の部位にあわせて、血液検査、腹部超音波検査、胃カメラ検査、大腸カメラ検査などの必要な検査を行い、出血部位の特定と原因を探っていきます。
痔核・裂肛が疑われる場合
血便の原因として一番多いのが、痔による出血です。痔の検査については、病歴や症状などの問診だけでは判断しにくい部分もあり、肛門の視診や触診を行う必要が出てきます。そのため、受診をためらってしまう方も多いのですが、痔の治療は早期に対応することで、侵襲の少ない施術で完治できる可能性が高いため、できるだけお早めに医師に相談していただくことを推奨しています。
胃カメラ検査
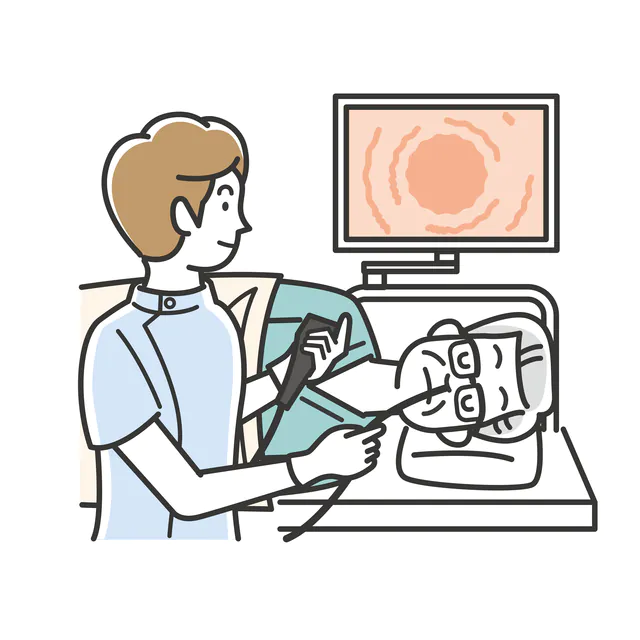 便からの出血が上部消化管による出血である可能性が疑われた場合、胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査では、食道、胃、十二指腸といった上部消化管の粘膜の状態を医師が目視で直接的に観察することができます。
便からの出血が上部消化管による出血である可能性が疑われた場合、胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査では、食道、胃、十二指腸といった上部消化管の粘膜の状態を医師が目視で直接的に観察することができます。
大腸カメラ検査
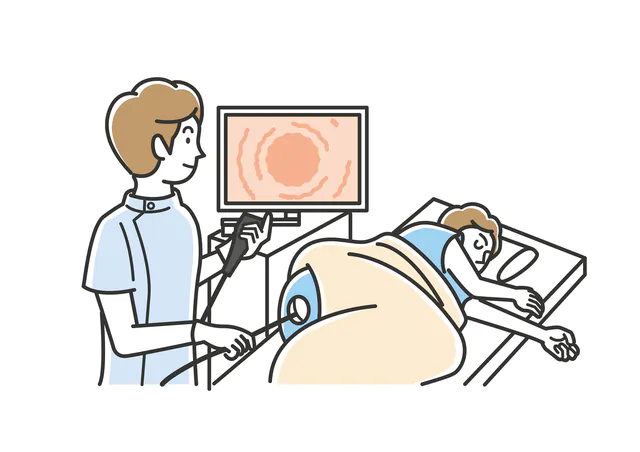 一方、腹痛、腹部膨満感、下痢、血便といった症状がある場合は、小腸から大腸にかけての下部消化管の病気が疑われます。小腸は、検査が難しい部位になってしまいますが、大腸に関しては、大腸カメラ検査で肛門から小腸との接合部あたりまでの粘膜の状態を細かく観察することが可能です。
一方、腹痛、腹部膨満感、下痢、血便といった症状がある場合は、小腸から大腸にかけての下部消化管の病気が疑われます。小腸は、検査が難しい部位になってしまいますが、大腸に関しては、大腸カメラ検査で肛門から小腸との接合部あたりまでの粘膜の状態を細かく観察することが可能です。
また、大腸がん、大腸ポリープ、大腸憩室炎、炎症性腸疾患などの特徴的な病巣を直接発見することができる唯一の検査です。当院では、大腸カメラ検査は可能ですが、小腸の病気が疑われる場合には、高度医療施設での特別な検査が必要になります。その場合は、当院と連携する医療施設を紹介して、スムーズな検査を受けることができるようにしています。

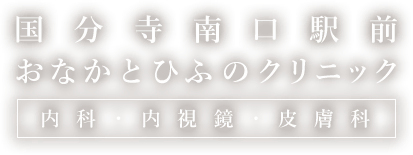





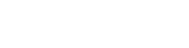




 痔には、いぼ痔、切れ痔、痔ろうなどの種類があります。
痔には、いぼ痔、切れ痔、痔ろうなどの種類があります。