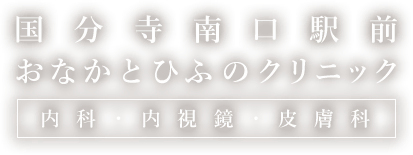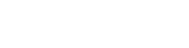皮膚のこんなお悩みはありませんか?
- 急に皮膚にできものができてしまったが、悪性のものでないか不安
-
前から気づいていたほくろやいぼが急に大きくなってきた気がする
-
皮膚にあるできものから出血している
-
皮膚のできものが化膿して腫れている、痛い
できものとは?
 できものは、皮膚のどこにでもできる可能性がある腫瘍や非腫瘍性のしこりなどのことで、医療用語ではそれらを総称して腫瘤と言っています。できものは種類によって色や形、硬さ、できやすい場所などに特徴があります。
できものは、皮膚のどこにでもできる可能性がある腫瘍や非腫瘍性のしこりなどのことで、医療用語ではそれらを総称して腫瘤と言っています。できものは種類によって色や形、硬さ、できやすい場所などに特徴があります。
最初は、痛み、痒みなどの自覚症状がほとんどあらわれないケースが多いのですが、大きくなったり、炎症を起こしたりすることで、皮膚から大きく盛り上がるなど見た目が変わってきたり、圧迫による違和感を覚えたりする他、痛みやにおいなどを感じるようになることもあります。
あまり悪化させないよう、お早めに当院の皮膚科までご相談ください。
できものの種類
できものには、腫瘍性のものや非腫瘍性のものなどの病理的な違いから、皮膚の表面にできるもの、内部にできるものなど多くの種類があります。さらに、腫瘍性のものの中にも良性のもの、悪性のものなどの区別があり、それらの種類をしっかりと特定して適切な治療を行う必要があります。
その中でも、皮膚にできる腫瘍性のできものには以下のようなものがあります。
皮膚良性腫瘍
- ほくろ
- 脂漏性角化症(老人性いぼ)
- 粉瘤
- 汗管腫
- 稗粒腫
- 脂肪腫
- 血管腫
- 軟性線維腫
- 石灰化上皮腫
- 皮膚線維腫
- エクリン汗孔腫
皮膚悪性腫瘍
- 基底細胞がん
- 扁平上がん
- 悪性黒色腫
- 日光角化症
- 隆起性皮膚線維肉腫
- 汗孔がん
- メルケル細胞がん
- Bowen病
様々な種類がある皮膚腫瘍ですが、良性と悪性の違いをしっかりと判別して適切に治療を選択することが特に大切です。
粉瘤(アテローム)
粉瘤は、毛穴や怪我の痕などの内側に皮膚が巻き込まれて袋状になってしまった良性腫瘍で、アテロームとも言います。内部には本来皮膚から排出されるはずの老廃物や皮脂が溜まっています。外部から触れるとしこりがあり、その中央に小さな出口の穴があることが特徴です。
最初はちょっとしたしこりのようなものですが、だんだん中に老廃物が溜まってくると大きくなり、強く押すと中身がしみ出して独特の臭気を放つようになります。
そのままの状態であれば痛みを感じるようなことは無く、できた場所によって何かが触れた時に違和感を覚える程度ですが、細菌に感染したり潰れたりすると炎症を起こし、強い腫れと痛みなどを感じるようになります。この状態を炎症性粉瘤と言い、医療機関でのすみやかな治療が必要になってきます。
粉瘤は、外見上ニキビと勘違いされることもありますが、あくまでも皮膚内にできた袋が本体で、自然に治ることは無く、完治するには袋状の本体を完全に取り除く必要があります。
粉瘤(アテローム)の原因
粉瘤が発症する原因
粉瘤は毛穴や傷痕など、皮膚に開いた穴の内側に表皮が巻き込まれて袋状になったものです。袋状の腫瘍ができる原因としては、足裏など毛穴の無い部分で、外傷によって皮膚が内側に入り込んでしまうケース、HPV(ヒトパピローマウイルス)感染の影響などはっきりしているものもありますが、ほとんどの場合原因をはっきりと説明することはできません。
中には粉瘤ができやすい方もいますが、遺伝ではなくその方の体質ではないかと考えられています。また粉瘤は身体のあちこちに多数できるケースもあります。
粉瘤の本体は袋状の腫瘍ですが、無症状だからといって放置しておくと、どんどん老廃物や皮脂などの中身が溜まって大きくなります。あまり大きくしてしまうと切開する部分も大きくなり、傷痕なども残りやすいため、お早めに治療することをお勧めしております。当院でも粉瘤の治療に対応しておりますので、いつでもご相談ください。
炎症を起こす理由
粉瘤が炎症を起こして腫れ上がってしまった状態を炎症性粉瘤と言います。炎症を起こす原因としては、袋状の本体が何かに触れるなどによって圧力を受けて潰れて内容物が皮膚内で拡がってしまうようなケースが最も多く、細菌感染が続いています。
細菌感染の場合は抗菌薬を使って炎症を鎮めることが可能ですが、潰れて内容物が飛び出したケースでは抗菌薬によって炎症を鎮めることができません。
いずれの場合でも炎症性粉瘤になった場合、すぐに本体である袋を取り除く治療はできません。いったん表面を切開して中身を出す、注射器で中身を吸い出すなどの処置を行い、感染症の合併を防ぐため抗菌薬を処方し、炎症が落ち着くのを待って、粉瘤本体を取り除く手術を行うことになります。
粉瘤はできるだけ早く摘出手術を
粉瘤はできものの中でもニキビ、感染性のおできなどと共にポピュラーな皮膚の病気の1つです。しかし、にきびやおできが自然治癒するものであるのに対し、粉瘤は自然治癒することは無く、手術で本体の袋を取り除くことが唯一の根治方法です。
放置して大きくしてしまうと、炎症を起こしやすくなる、何かに当たって違和感が強くなる、独得の臭気が出るなどで日常生活に差し障りがあるだけではなく、手術で切開する範囲も広くなってしまい、皮膚に傷痕を遺さず治療することが大変難しくなることもあります。
そのため、皮膚に小さなしこりがあり、中央に小さな穴があるような状態を見つけた場合、お早めに当院の皮膚科にご相談いただくことをお勧めしています。
粉瘤(アテローム)の治療
 粉瘤の切除手術には、くり抜き法と切開法の2つがあり、状態によってどちらかの方法を選択することになります。
粉瘤の切除手術には、くり抜き法と切開法の2つがあり、状態によってどちらかの方法を選択することになります。
どちらの方法でも局所麻酔を行いますが、当院では患者様の痛みを極量少なくするため、極細の麻酔針を使うなどの配慮をしております。
くり抜き法
穴あけパンチのような特殊な器具を使って皮膚に粉瘤の大きさより小さな孔を穿ち、そこから内容物を出した後、中を削るように袋状の本体を全て掻き出します。
切開創が小さく仕上がりはきれいになり、また手術時間も短くてすみます。手術にかかる時間は5~20分程度です。通常は切開創を縫合しなくて済むため、抜糸もありません。
切開法
粉瘤の形を見極めて皮膚に切開する範囲をマーキングした上で、メスで切開し粉瘤全体を取り出します。
傷痕は大きくなり、縫合・抜糸も必要になりますが、再発率はくり抜き法よりも低く、粉瘤の大きさなどによって切開法をお勧めすることもあります。
粉瘤(アテローム)手術までの流れ
ご予約
粉瘤治療ご希望の方はWEBまたは電話にて事前にご予約ください。
診察
まずは、粉瘤の状態を拝見し、大きさや炎症の有無などを確認して、すぐに手術可能かどうかなどを判断します。当日の手術が可能な状態であれば手術に進み、炎症がある場合は、内容物を出して抗菌薬などを処方した上で、炎症が鎮まるのを待ち、後日の手術となります。
手術
手術は、患者様の状態によってくり抜き法か切開法かを選んで、局所麻酔をした上で施術します。時間は5~20分程度です。
術後
手術が完了したら、患部にガーゼを貼って保護した上でご帰宅いただけます。人によって異なりますが、一般的に1~3日程度はガーゼが出血で汚れますので、毎日交換してください。ガーゼに汚れが付かなくなったら、ガーゼではなくテープでの保護に変更してください。
ガーゼ交換の際にシャワーで創を優しく流す程度であれば大丈夫ですが、入浴は感染予防のため抜糸までは控えてください。なおくり抜き法で縫合しなかった場合、通常は手術翌日から入浴可能になります。
その後は、指定された日程で、経過を診るためにご来院ください。
なお、炎症性粉瘤の手術を行った場合は、この記述より予後のケアの日程が長引くことになります。
合併症
当院では、できるだけ術創が目立たないよう、切開やくり抜きの方法などに配慮はしておりますが、皮膚を切開し、袋状の腫瘍をくり抜いて取り出すことになりますので、くり抜き法でも切開法でも多少は傷痕が残ってしまいます。また、手術後1週間程度で術創が硬くなってくることがありますが、しばらくすると元に戻りますのでご安心ください。ただし、人によっては瘢痕化してしまうケースもありますので、なかなか元に戻らないようならご相談ください。
出血予防のため、手術当日と翌日は飲酒や運動を控えてください。また入浴については、くり抜き法の場合は手術翌日から可能になりますが、切開法の場合は抜糸まではシャワーで流す程度に留めてください。
感染予防などのために処方するお薬については、指定通り服用・塗布をお願いします。ただし、人によってはアレルギー反応などが出る場合もありますので、その場合はすぐに当院までご相談ください。
いぼ
 いぼは皮膚から盛り上がったできものの一種の総称で、医療用語では疣贅(ゆうぜい)と言い、誰にでもできる可能性がある皮膚の病気です。
いぼは皮膚から盛り上がったできものの一種の総称で、医療用語では疣贅(ゆうぜい)と言い、誰にでもできる可能性がある皮膚の病気です。
いぼには尋常性疣贅、老人性疣贅、伝染性軟属腫、扁平疣贅、尖圭コンジローマといった種類がありますが、ウイルスが原因となるものと、ウイルス感染以外の原因でできるものに分類できます。
いぼができる原因
いぼができるのは、ほとんどの場合ウイルス感染によるものです。特にHPV(ヒトパピローマウイルス)感染によるものが多いですが、その他にもいぼを発症するウイルスは100種類以上にも上ると考えられています。小さい傷などから皮膚内にウイルスが入り込むことで発症します。
いぼの症状
尋常性疣贅
皮膚の小さな傷からHPVに属するウイルスが侵入、感染することでその部分の細胞が増殖していぼになります。好発部位は、傷の付きやすい手指、足指や足裏などの他、痒みで掻いてしまうことの多い腋の下や肘などです。当初は小さな盛り上がりがだんだん大きくなり数mmから大きくて2cm程度のいぼとなります。中にはウイルスがつまっており、掻き潰してしまうといぼが拡がったり他者にうつしたりすることがありますので注意が必要です。
足底疣贅
HPV感染によってできる足裏のいぼのことで、尋常性疣贅の一種と考えられています。体重がかかる部分ですので歩くと痛むことがありますが、患部を直接触った場合には痛みはありません。だんだん平らになっていきますが、皮膚が分厚く硬い状態になり、皮膚の色は白から黄色くなります。見た目からウオノメやタコと間違えて削ってしまうと出血してしまうため注意が必要です。
いぼの治療
一般的に、ウイルス性のいぼの治療は液体窒素による冷凍凝固療法と、いぼ剥ぎ法による切除療法があり、どちらも健康保険が適用されます。
液体窒素治療
-196℃という超低温の液体窒素によって患部を凍らせ、溶かすという方法を何度か繰り返すことによって、患部の細胞を破壊していぼを除去します。液体窒素を綿棒に浸して患部に付けたり、スプレーで患部に拭きかけたりする方法ですが、痛みが生じることや、1週間に1度の治療を何回か繰り返す必要がある点に注意が必要です。
当院では、液体窒素治療に対応しております。
いぼ剥ぎ法
患部周辺に局所麻酔をして、いぼの周辺の皮膚にメスで切れ込みを入れて、特殊な器具を差し込んでいぼを底辺から剥ぎ取るように切除します。切開創は縫合せず特殊なテープで保護します。治療は1度だけで済みますが稀に再発します。ただし、再発した場合もいぼの大きさは確実にほとんど目立たないほどまで小さくなります。