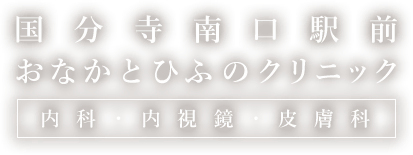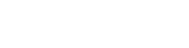受診した方がよい下痢の症状とは
- 水のような便や泥状の形の無い便が続いている(シャーシャーの下痢)
-
腹痛と下痢が長期間続き、なかなか治らない
-
下痢に血液らしいものが混じっていた
-
下痢状態が続き、トイレに通う回数が明らかに増えている
-
便秘をしていて、便通がある時は下痢状の便が少しずつ出る
続く下痢、受診の目安は
下痢は、2週間程度で治る急性下痢と4週間以上続く慢性下痢に分けられます。
しかし、ウイルスや細菌による感染や薬剤などによる下痢は、多くの場合は1週間程度で治るものです。
2週間以上経っても下痢が治らないようなら、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸炎、大腸がんなどの重篤な病気や、過敏性腸症候群などの可能性もあります。その場合は検査を受けることをお勧めします。
下痢とは
 下痢とは、便の水分が大腸で十分に吸収されず、水または泥のような状態で排泄されることです。腹痛を伴うものも多いのですが、腹痛の無い下痢もあります。
下痢とは、便の水分が大腸で十分に吸収されず、水または泥のような状態で排泄されることです。腹痛を伴うものも多いのですが、腹痛の無い下痢もあります。
原因は、大腸へのなんらかの刺激による運動機能や消化吸収機能の障害で、細菌・ウイルス等への感染、内分泌異常、薬剤による刺激、ストレスなどによる自律神経の異常などが考えられます。その裏には、なんらかの重篤な病気が隠れていることもあります。原因を特定するためにも、一度当院までご相談ください。
軟便と下痢の違い
軟便は、一般的な便よりは水分が多いけれど、下痢まで至らないという中間の便です。一般的に理想的な便はバナナ状と表現されるもので、水分の含有率が70~80%程度とされています。これに対し、下痢便は水分が90%以上のもの、軟便は80~90%程度のものを指し、水分が多いため、形になりかかってはいますがドロっとしており、排便時に残便感が残りやすいことが特徴です。
波のある腹痛を伴う下痢になったら
キューっとした痛みを感じ便意を催すが、しばらくすると治まってくる下痢は、腸管の動きが亢進するなどの腸の動きに関連した下痢である可能性が高くなります。
例えば、蠕動運動が亢進したり鎮まったりする場合、激しく亢進した際に便は早く進み強い便意となり、亢進が鎮まると便意は落ち着きます。こうした症状は、過敏性腸症候群の下痢型や急性胃腸炎などに起こる症状で、重篤な病気である可能性は低いです。しかし、他の病気が関連している可能性が無いとは言えませんので、一度検査を受けておくことをお勧めします。
下痢の原因
腸管蠕動運動の異常
蠕動運動が激しくなりすぎると、便の通過速度が速すぎることで腸壁から十分水分を吸収できず下痢となります。主な原因は、自律神経のうち副交感神経が優位になりすぎることです。
この症状を起こす病気としては
- 過敏性腸症候群
- 甲状腺機能亢進症
- 虚血性大腸炎
など
この病気の他に、がん性腹膜炎などでも見られることがあります。
腸管内の炎症
大腸粘膜に炎症が起こると、炎症によって便中の水分吸収が十分にできないことや、腸壁の炎症による障害を修復・保護しようとして滲出液が多量に分泌されることで、便中の水分が多い状態が続き、下痢を起こします。下記のようなものが代表的な原因です。
- 細菌・ウイルスなどによる感染症腸炎
- 潰瘍性大腸炎、クローン病に代表される非特異的炎症性腸疾患
- 胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害約、H2ブロッカー)、抗生剤などの副作用
- 膠原病
感染性腸炎
腸がウイルスや細菌、及びその毒素に感染した場合、急激に下痢を起こすことが多くなります。原因となる主な病原体としては、ノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルス、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、O157などの病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌やボツリヌス菌などが賛成する毒素です。
これらの病原体に感染する経路としては経口感染が多く、以下に挙げるものが主な感染経路となります。
- これらに汚染された食品や飲料を口にした
- 子どもと親の口移しによる経口感染
- 性行為など人から人への接触感染
- 動物との接触による感染
なお、潜伏期間は数時間~10日程度と病原体によって異なりますが、一般的に毒素によるものは潜伏期間が短い傾向にあります。
薬剤による副作用
治療のための処方薬であっても、長く続けたり、体質に合わなかったりして副作用から腸に炎症を起こし下痢となることがあります。腸炎を起こしやすいのは以下のようなお薬です。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI)、ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)などの胃酸分泌抑制薬
- 抗菌薬(抗生物質)
- 下剤
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬などの抗炎症薬、解熱鎮痛薬
- 抗がん剤
栄養不足・低アルブミン血症
アルブミンは肝臓で産生されるたんぱく質の一種で、血液中の水分を保持する役割を果たしています。アルブミンが不足すると血管から水分が漏れ出し、下痢になることがあります。原因としては、肝炎、肝硬変、肝不全などによって肝臓でアルブミンを上手く産生できないことや、糖尿病性腎症、慢性腎臓病(CKD)、ネフローゼ症候群などによる血中からのアルブミン喪失によるものが考えられます。
下痢の検査・診断
問診によって、症状がいつごろからあらわれ、どのような程度であるか、便の状態と1日の排便回数、血液混入の有無などについて詳細に伺います。
その結果を受けて必要な検査を行います。感染の有無や炎症の状態などについては血液検査で、大腸の粘膜の状態については大腸カメラ検査で、消化管以外の消化器については腹部超音波検査などによって、詳しく検査を行って原因を特定していきます。
下痢の治療
下痢の治療としては、薬物療法、脱水防止、腸管安静、生活習慣改善の4つの方法を主に行います。
ただし、炎症性腸疾患、がんなどの明確な原因疾患がある場合は、下痢による脱水を防止しながら、原因疾患の治療を優先して行います。
薬物療法
下痢を起こしている原因に合わせて適切な薬を使用して治療を行います。感染性の下痢の場合、ウイルス感染や細菌の産生した毒素によるものでは対症療法(水分補給や抗炎症薬の使用など)で対応しますが、細菌感染の場合は抗菌薬を処方することもあります。感染性の場合、下痢止めを使用することで、病原体の排出が遅れ、治りが遅くなることもあります。そのためなるべく使用せずに治療を行います。その他の病気による場合は適宜使用することもあります。
水分補給と点滴
下痢によって体内の水分が失われてしまうことが無いよう、適宜水分補給を行っていきます。
水を大量に補給した場合、浸透圧異常を起こしてしまうこともあるため、経口補水液を積極的に摂取します。しかし、重症の場合はご自身での補水ができないことも多く、入院の上、点滴で水分補給を行うことがあります。その場合は、当院が連携している高度医療機関をご紹介させていただきます。
生活習慣の乱れ・極度の精神的ストレス
 下痢は、無理な食生活や食事内容、不規則な生活習慣から誘発されることがあります。また、ストレスや過労などによる精神的影響から自律神経が乱れて起こることもあります。この理由としては、全ての消化管の運動機能が自律神経によって調整される平滑筋で構成されているからです。当院では、日常生活の改善、ストレスコントロールなどについて、丁寧に指導させていただいています。
下痢は、無理な食生活や食事内容、不規則な生活習慣から誘発されることがあります。また、ストレスや過労などによる精神的影響から自律神経が乱れて起こることもあります。この理由としては、全ての消化管の運動機能が自律神経によって調整される平滑筋で構成されているからです。当院では、日常生活の改善、ストレスコントロールなどについて、丁寧に指導させていただいています。