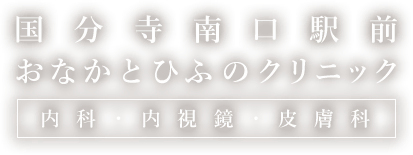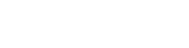便秘について
便秘とは、便を長期間排泄することができない状態、または排便はできても不満感が残るような状態を言います。
人によって適切な排便期間は異なりますが、一般的には3日程度排便の無い状態を指します。
便秘があると腸に負担がかかり、おなかの不調が起こるだけではなく、全身に不調の影響が及ぶ可能性もあります。
便秘の原因
便秘には、腸管の炎症やがんなどの器質的な病気や内分泌的な異常、薬剤による刺激など何らかの外的要因によって起こるもの、特に外的な異常が無く消化管の運動機能や知覚機能に異常があって起こるものがあります。
特に、外的刺激が無い便秘を機能性便秘と言い、大腸の蠕動運動が弱まって便が肛門へ運ばれないもの、腸管の知覚機能の異常により大腸の動きが不規則になることで腸管が痙攣して起こるもの、直腸に便が溜まった際に排便を起こしてくれる排便反射がないことによるものがあります。
これらの便秘が起こる原因としては、肥満や運動不足などの生活習慣、食事の量が少な過ぎる、便意を我慢し過ぎる、ストレスや過労などによって自律神経が乱れるなどが考えられます。
便秘の症状
- 気がつけば何日も排便していない
- 排便は規則正しくあるが、何か残っているようなすっきりしない感じ
- おなかが張る
- ガスが溜まっておならが出やすくなった
- 便意を感じてトイレに行くが、結局出ない
- おなかが張って吐き気がする
- 腹痛がある
- 食欲が出ない
- 左下腹部を触ると棒状のものがある
便秘による体の変化
においのトラブル
便秘では、便が腸内に長時間滞留することで腐敗が進み、腸内でガスが発生します。
このガスには毒性のある化学物質が含まれており、それが血管に吸収されて全身に回ることで、呼気に混ざって排出されたり皮膚から排出されたりします。そのため、口臭や体臭の原因となる可能性があります。
お肌のトラブル
 便が長時間滞留することで、腸内細菌のうちの悪玉菌と呼ばれる菌によって腐敗が進みます。悪玉菌から産生される物質には、アンモニアなどの有毒物質が含まれています。この有毒物質が腸壁から血管へと吸収されて全身に回り、前項のように悪臭となる場合もありますが、皮膚などに蓄積して皮膚の代謝を滞らせ、肌荒れ、吹き出物、ニキビといったお肌のトラブルが発生します。
便が長時間滞留することで、腸内細菌のうちの悪玉菌と呼ばれる菌によって腐敗が進みます。悪玉菌から産生される物質には、アンモニアなどの有毒物質が含まれています。この有毒物質が腸壁から血管へと吸収されて全身に回り、前項のように悪臭となる場合もありますが、皮膚などに蓄積して皮膚の代謝を滞らせ、肌荒れ、吹き出物、ニキビといったお肌のトラブルが発生します。
太りやすい体質
 肝臓は、身体活動に必要な栄養素の合成・蓄積、老廃物の解毒、胆汁の生成と大きく3つの役割を果たしています。それぞれの働きにはエネルギーが必要ですが、慢性的に便秘があると、便の腐敗によって作られる毒素を分解するためにエネルギーを消費し過ぎてしまいます。そのため、代謝不良などを起こし太りやすくなる傾向があります。
肝臓は、身体活動に必要な栄養素の合成・蓄積、老廃物の解毒、胆汁の生成と大きく3つの役割を果たしています。それぞれの働きにはエネルギーが必要ですが、慢性的に便秘があると、便の腐敗によって作られる毒素を分解するためにエネルギーを消費し過ぎてしまいます。そのため、代謝不良などを起こし太りやすくなる傾向があります。
疲労感とストレス
機能性の便秘は、大腸の運動機能や知覚機能の異常が原因となっていることが多いです。そ
れによって、便が腸管内に長い間滞留することで、おなかの張り、痛み、残便感など様々な不快感を伴うことになります。
その不調によって、身体を動かすのが億劫になることで運動不足に陥り、さらに便秘になってしまうという悪循環に陥ることがあります。
免疫力低下
腸内細菌を構成する善玉菌は、乳酸や酢酸を作成して腸内を酸性にすることで、細菌やウイルスに感染しにくくする働きをしています。
これを腸管免疫と言いますが、便秘によって悪玉菌が多くなると、この免疫機能が上手く働くことができなくなり、感染症などへの抵抗力が弱まってしまう可能性があります。
このような便秘は来院を
快適な排便習慣というのは個人差があるため、どのような症状であれば便秘と言えるかは原則決まっていません。一般的に、3日以上便が出ない、市販や処方された下剤を使って1~2日を経ても排便が無い、強い腹痛、吐き気や嘔吐、膨満感によって活動意欲が低下するなどの症状がある場合は、一度ご相談いただくことをお勧めします。
また、便秘に伴う症状の中には、機能性の便秘ではなく、器質性のものや内分泌異常によるものもあります。さらに、器質性の便秘の中には、がんや前がん病変の大腸ポリープが気づかないうちに大きくなっており、排便障害を起こしている場合や何らかの外圧によって腸閉塞を起こしかけている場合などもあります。突然の強い腹痛、嘔吐、激しいおなかの張りといった危険な徴候があらわれる場合もありますので、いつもと異なる排便に関する症状を感じた時は、お早めにご相談ください。当院では、様々な治療の選択肢を患者様と一緒に検討していくことが可能です。
便の形や性質を把握しておくことは、医師にとって貴重な判断基準にもなります。
便は汚いと思わず、排便のあった時刻、排便の状況、便の形状や硬さなどについて詳細に記録しておくことをお勧めします。
以下に、国際的な消化器病学会が提唱する、便の形状・性状による診断のためのブリストル便形状チャートに従った特徴を例示していますので、参考にしていただければと思います。
| タイプ | 形状 | 評価 |
|---|---|---|
| タイプ1 | 兎糞状のコロコロとした形状 | 便秘傾向 |
| タイプ2 | コロコロした兎糞が固まったソーセージのような形状 | |
| タイプ3 | ソーセージのような形状で、表面にややひび割れができている硬い便 | |
| タイプ4 | 表面がやわらかで、バナナのような柔軟な形状、またはとぐろを巻くような形状 | 正常 |
| タイプ5 | 少し柔らかいが、境界ははっきりとしており、半固形状の便 | |
| タイプ6 |
柔らかく泥のような便 |
下痢傾向 |
| タイプ7 | 形が無く水のような便 |
便秘の治療
便秘は主観的な部分も多く、毎日きちんと便が出るかどうかより、患者様ご本人が排便に満足感を得ることができるかどうかを重点にして治療を行います。何らかの病気によって起こる便秘の場合は、原因となる病気の治療を第一に考えながら、便秘の辛い症状に対する薬物療法を検討します。
一方、機能性便秘の場合は、便秘の発症要因となっている生活習慣の改善に取り組みます。辛い症状に関しては、内服薬、坐薬、浣腸などの便秘薬で対応、または予防していきます。
薬の種類
便秘のお薬は、便秘の機序を利用して様々な種類のものが開発されています。そのため、患者様の便秘の状態やタイプに合わせてお薬を処方します。
具体的には、便に水分を補給し硬い便を和らげる酸化マグネシウムや、腸の蠕動運動を刺激して便の流れを促進するセンナ、腸からの分泌液を増やして便を柔らかくする機能性脂肪酸の一種(ルビプロストンなど)の処方を検討します。
便秘になったら
便秘の発症要因には、食生活を含む生活習慣が大きく関わっています。
そのため、生活習慣を改善することで便秘も改善して行くことが期待できます。ここでは、便秘改善に効果のある生活習慣について説明します。
1)できる範囲で体を動かす
 激しい運動は必要ありません。ご自身でできる範囲の適切な運動は、腸管の運動を促進する上でも効果があります。お勧めの運動としては、ウォーキングやジョギングなど、特別な準備をせずにできる有酸素運動、ゆっくりと無理なく行うスクワットなどのレジスタンス運動などです。病気の療養などで外出などが難しい場合には、ベッドの上で身体を動かす、トイレまでゆっくり歩くなどでも十分な運動になります。
激しい運動は必要ありません。ご自身でできる範囲の適切な運動は、腸管の運動を促進する上でも効果があります。お勧めの運動としては、ウォーキングやジョギングなど、特別な準備をせずにできる有酸素運動、ゆっくりと無理なく行うスクワットなどのレジスタンス運動などです。病気の療養などで外出などが難しい場合には、ベッドの上で身体を動かす、トイレまでゆっくり歩くなどでも十分な運動になります。
歩ける方も歩けない方も、有効な対策として、おなかの外周を「の」の字を描くようにゆっくり優しくマッサージすることや、おなかを温湿布などで温める方法もあります。
2)水分を摂取する
トイレに通うことを気にして、水分摂取を制限してしまう方がいます。これは便通にとって大敵です。
積極的に水分を補給すると、便の水分も増えて排泄しやすくなります。一般的な1日の水分補給量としては1.5L程度が推奨されています。
3)食物繊維をとるなどの食事を工夫する
 適度に体を動かし、水分を摂取していても便秘が続く場合には、食物繊維(特に水溶性食物繊維)を多く含んだものを食べることが効果的です。食物繊維は、主に豆、きのこ、海藻、果物などに多く含まれます。ただし、体の状態によっては摂りすぎるとよくない場合もあるので、医師と相談しましょう。また、乳酸菌などの生きた微生物を含む食品(ヨーグルト、納豆など)は、適正な量を摂ることで便秘を和らげる効果があると言われています。
適度に体を動かし、水分を摂取していても便秘が続く場合には、食物繊維(特に水溶性食物繊維)を多く含んだものを食べることが効果的です。食物繊維は、主に豆、きのこ、海藻、果物などに多く含まれます。ただし、体の状態によっては摂りすぎるとよくない場合もあるので、医師と相談しましょう。また、乳酸菌などの生きた微生物を含む食品(ヨーグルト、納豆など)は、適正な量を摂ることで便秘を和らげる効果があると言われています。
病気の状態によっては食事や水分の制限もありますので、医師と相談しながら、食べられるものをバランスよく食べることが大切です。
4)落ち着いて排便できる環境を整える
トイレの環境も排便に大きく影響します。環境が悪ければトイレの時間は落ちつかず、ゆっくり便を出すことができなくなります。また、便意を感じても環境が悪いことで、つい我慢してしまうこともあり、便秘を助長することになります。もちろんトイレに長居し過ぎるのもよくありませんが、トイレの環境を整えることは快適な排便に繋がります。
5)生活リズムを整えるなどのその他の工夫
食事や睡眠の時間が不規則になると、排便するまでの一定のリズムを築けなくなります。毎日規則正しい生活を送ることで、自然に排便の時間も一定してきます。
なお、西洋式便器はそのまま座ると、背筋が垂直になって腸の出口が緩まなくなります。西洋式便器に座る場合は、前かがみになることで排便しやすくなります。