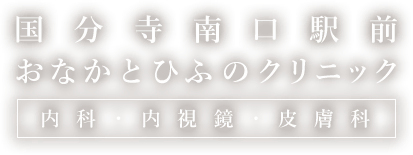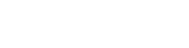便潜血検査が陽性だったら
 便潜血検査は、便の中に肉眼で見えないような血液が混じっていないかどうかを確認するための検便検査で、消化管に何らかの障害が起きているサインとなる大切な検査でもあります。
便潜血検査は、便の中に肉眼で見えないような血液が混じっていないかどうかを確認するための検便検査で、消化管に何らかの障害が起きているサインとなる大切な検査でもあります。
便潜血が陽性であった場合、食道から肛門までの消化管のどこかから出血があったことを示します。ここでは、便潜血検査で分かることと、陽性であった際に受けるべき精密検査についてご説明します。
便潜血検査の検査方法とわかること
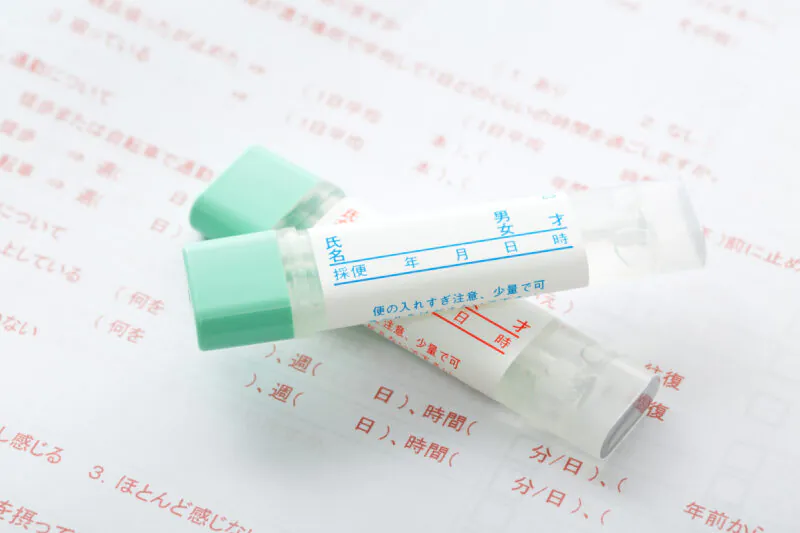 便潜血検査は、企業や団体が行う定期健診や、地方自治体が行う特定検診などの標準的な検査項目となっています。上記の通り、消化管のどこかから出血があったことを示す検査ですが、主に大腸の異常、特に大腸がんのスクリーニング検査として行われます。
便潜血検査は、企業や団体が行う定期健診や、地方自治体が行う特定検診などの標準的な検査項目となっています。上記の通り、消化管のどこかから出血があったことを示す検査ですが、主に大腸の異常、特に大腸がんのスクリーニング検査として行われます。
そのため、各地方自治体で定期的に行われる簡易的な大腸がん検診でも、この検査が導入されています。この場合は、公費補助によって自己負担を少なくできます。
大腸がんやその前がん病変である大腸ポリープの組織は、非常に脆く、硬い便と擦れることで少量の出血が起こることがあります。通常、肉眼ではわからない程度の出血ですが、この検査は赤血球の成分であるヘモグロビンを検出するもので、ごく少量の出血でも見つけ出すことができるため、これらの病変がある可能性を早期に確認することができます。
なお、国分寺市では、この40歳以上の方には毎年自己負担無し(無料)で検査を行っています。当院でもこの検査に対応していますので、対象期間内にいつでもご相談ください。詳細につきましては国分寺市のWEBサイトなどをご確認ください。
便潜血検査のメリットとデメリット
便潜血検査は、バリウム検査や大腸カメラ検査のような事前準備や当日朝の絶食も必要がないシンプルな検査です。そのため、大腸粘膜の病気のスクリーニング検査として多くの健康診断で採用されています。
ただし、痔の出血があったり月経中であったりすると陽性になってしまうことや、消化管のどの部分に何の病気で出血しているのかまでは分からないなどのデメリットもあります。
しかし、痔や月経中でなくこの検査で陽性だった場合は、消化管のどこかに障害が起こっていることは確かですので、自己判断せず必ず精密検査を受けてください。また、進行がんがあったとしても常に出血しているとも限りません。便潜血が陰性であっても、定期検診をきちんと受けるようにしましょう。
便潜血陽性の精密検査って何をする?
 便潜血検査が陽性になると、結果説明時に要精密検査と判定されます。痔のある方でも、便潜血検査の採取時に月経だった方でも、出血の原因を自己判定することはお勧めいたしません。大腸がんがあった場合でも、自覚症状があらわれにくい病気であるため、必ず精密検査を受けることが大切です。
便潜血検査が陽性になると、結果説明時に要精密検査と判定されます。痔のある方でも、便潜血検査の採取時に月経だった方でも、出血の原因を自己判定することはお勧めいたしません。大腸がんがあった場合でも、自覚症状があらわれにくい病気であるため、必ず精密検査を受けることが大切です。
精密検査では、一般的には大腸カメラ検査、または大腸CT検査を行います。大腸カメラ検査は肛門からスコープを挿入し、大腸全体の粘膜の状態を直接的に観察できる検査で、疑わしい病変を見つけた場合には、その場で採取し病理検査に出すことが可能です。一方、大腸CT検査は、肛門から炭酸ガスを注入し、腸管を膨らませて大腸を細かくスライスするように撮影します。その撮影画像をもとに、病変の有無や位置を特定していく検査です。ただし、病理検査が必要な場合は再度大腸カメラ検査が必要になることがあります。
また、当院では大腸CT検査を行っていないため、検査が必要と判断した場合は当院と連携している高度医療機関をご紹介させていただきます。
当院の大腸カメラ検査
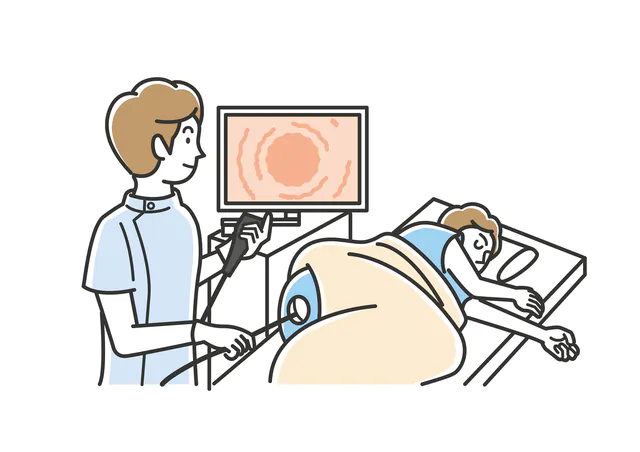 大腸カメラ検査は、病変があれば高い精度で発見することが可能な検査です。しかし、「辛そう」「お尻を出すのが恥ずかしい」などと躊躇ってしまう方が多いです。
大腸カメラ検査は、病変があれば高い精度で発見することが可能な検査です。しかし、「辛そう」「お尻を出すのが恥ずかしい」などと躊躇ってしまう方が多いです。
当院では、まずは患者様のプライバシーの配慮を徹底しています。また、検査自体も様々な工夫を行って、できるだけ短時間のうちに正確な検査を済ませることができるようにしています。また、より苦痛を最小限にしたい方は、鎮静剤を使って、眠っているような状態のまま検査を行う方法もご用意していますので、安心してご相談ください。
便潜血検査で発見できる病気
大腸がん
大腸がんの多くは、腺腫と呼ばれる悪性化しやすい腫瘍性の大腸ポリープを放置することによって、一定の確率でがん化して起こります。稀に、正常な粘膜が直接がん化してしまうこともあります。
好発部位は、直腸からS状結腸にかけてですが、横行結腸や上行結腸、盲腸にできることもあります。
早期にはほとんど自覚症状は無く、少し進行するとがん化した部分が便と擦れて出血し、血便や潜血便があらわれることがあります。
さらに、悪化し大きくなると、便の通り道を塞いでしまうため、腹部膨満感、腹痛、便秘、嘔吐などの症状があらわれます。
治療は、早期のうちであれば、大腸カメラのスコープについた処置器具で切除するだけで完治が可能です。しかし、進行すると浸潤・転移しやすいため、極めて治療が難しくなりますので、早期発見が重要となります。
便潜血検査陽性の方の2~4%程度が、大腸がんと診断されるという報告もあります。
痔
 痔には痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔瘻(穴痔)の3種類があり、それぞれ発症の仕組みや症状が異なりますが、多くの場合、便秘、下痢などの排便異常、排便時のいきみ、座りっぱなしの姿勢などに関連して肛門に負担がかかることで発症します。
痔には痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔瘻(穴痔)の3種類があり、それぞれ発症の仕組みや症状が異なりますが、多くの場合、便秘、下痢などの排便異常、排便時のいきみ、座りっぱなしの姿勢などに関連して肛門に負担がかかることで発症します。
以下に3つのタイプの痔の特徴を説明します。
痔核 (いぼ痔)
痔核は、一般的にはいぼ痔と言われるもので最も多いタイプで、肛門の直腸側にできる内痔核、皮膚側にできる外痔核に分けられます。
どちらも、肛門近辺にあってクッションの役割をしている静脈叢と呼ばれる血管が集まった部分の血流異常が原因でイボ状に膨らんでしまうことが原因で発症します。内痔核は脱肛や出血が特徴ですが、痛みはあまりありません。一方、外痔核の出血はあまり多量ではありませんが、痛みを伴います。
裂肛(切れ痔)
便秘で太く硬くなってしまった便を無理矢理押し出したり、激しい下痢で肛門に負担がかかったりすることで、肛門が裂けてしまった状態です。痛みは伴いますが、それほど出血は多くありません。便通異常を起こしやすい女性に多いタイプの痔です。
痔ろう(穴痔)
肛門の直腸と皮膚側の境目には歯状線という繋ぎ目があり、その部分は溝状に少しくぼんでいる肛門陰窩と呼ばれるものがあります。肛門陰窩の奥には肛門腺と呼ばれる、粘液の分泌線があります。通常は、この部分に便が入り込むことはありませんが、激しい下痢などを繰り返すことで便が入り混んでしまい、肛門腺に感染が起こって化膿します。この状態を痔瘻の前段階である肛門周囲膿瘍と言い、痛み、発熱、腫れなどのつらい症状があります。また、肛門陰窩にある膿は、肛門近くの皮膚を破って膿が排出されます。この状態が痔瘻で、排出された穴は塞がることが無く、そのまま残ります。その状態では、症状はそれほど辛くありませんが、非常に再発を繰り返しやすく、そのたびに瘻管(痔瘻でできた穴)が枝分かれを繰り返し、徐々に複雑化していきます。治療は手術のみですが、早めに行わなければ、手術もどんどん難しいものになります。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、腫瘍性のものと非腫瘍性のものに分けられます。そのうち、腫瘍性の腺腫というポリープが一番多く、放置することにより一定確率でがん化してしまうため、前がん病変とも呼ばれています。ポリープがあってもほとんど自覚症状は無いことや、大腸がんより出血することが少ないことから、便潜血検査で発見されることも多くはありません。大腸カメラ検査を受けた際に、偶然発見されることが多く、将来のがん化を予防することもできるため、その場で切除することを推奨しています。ただし、非常に小さいポリープでがん化の徴候が見られない場合は経過観察とし、また、大きくなりすぎている場合や数が多い場合は、出血を合併する可能性が高いため、入院して合併症を管理しながらの手術とすることになります。なお、当院では当日の日帰り手術のみ行っています。入院が必要になった場合は、連携する高度医療機関をご紹介し、スムーズな治療ができるようにしています。
大腸ポリープ自体は良性のものですが、放置することによって様々な症状があらわれたり、がん化してしまうことがありますので、定期的に大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。