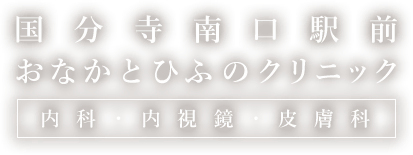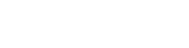おならとは
おならは、腸内の気体が肛門から排出される自然現象です。成分は約70%が飲み込んだ空気で残りの約30%が胃や腸で消化の際に発生したガスです。
それらの気体は、ほとんどが消化管の粘膜から吸収され、残りがげっぷやおならとなって排出されます。
そのためおならが増える理由としては、早食いなどで空気を飲み込みすぎることや、炭酸入りの飲料を飲み過ぎること、体調を崩して腸内の細菌叢に変化があったことなどが考えられます。
おならが作られる過程。
ニオイはどこでつくの?
 おならの成分は前述の通り、約70%が窒素、酸素、二酸化炭素など飲み込んだ空気で、残りが消化管で発生する水素、メタンなどのガスです。これらのガスのほとんどは、腸内の細菌叢(フローラ)が食物を消化する過程で発生するもので、空気の成分や多くの腸内ガスは無臭のものです。
おならの成分は前述の通り、約70%が窒素、酸素、二酸化炭素など飲み込んだ空気で、残りが消化管で発生する水素、メタンなどのガスです。これらのガスのほとんどは、腸内の細菌叢(フローラ)が食物を消化する過程で発生するもので、空気の成分や多くの腸内ガスは無臭のものです。
しかし腸内細菌叢には悪玉菌と呼ばれる細菌群もいて、悪玉菌はアンモニアやインドール、スカトールなどを発生させるため、おならのにおいの素ともなっているのです。
私達は毎日およそ7~20回ぐらいおならを出していますが、この回数が極端に増える、減る、においがきつくなるなどの変化がある場合、体調の変化が関係しており、食べ過ぎ、飲み過ぎなどの他に何らかの病気が関係していることも考えられますので、一度当院までご相談ください。
おならの原因
悪玉菌が増加する食事
 獣肉、鶏卵など動物性たんぱく質は悪玉菌の餌となるため、摂り過ぎると悪玉菌が優勢になってしまいます。それによって、アンモニアなどのにおい成分が含まれたガスが産生され、おならは臭くなってしまいます。また脂肪分の多い食物も消化に時間がかかり、その分腸内で腐敗が起こってにおいの素となります。たんぱく質や脂質は大切な栄養素ですが、偏らないよう、バランス良く食べるようにしましょう。
獣肉、鶏卵など動物性たんぱく質は悪玉菌の餌となるため、摂り過ぎると悪玉菌が優勢になってしまいます。それによって、アンモニアなどのにおい成分が含まれたガスが産生され、おならは臭くなってしまいます。また脂肪分の多い食物も消化に時間がかかり、その分腸内で腐敗が起こってにおいの素となります。たんぱく質や脂質は大切な栄養素ですが、偏らないよう、バランス良く食べるようにしましょう。
豊富な食物繊維
食物繊維は便の量を増やし便通を整えたり、余分な脂肪分や糖などを付着させて体外に出したりと、腸内環境を整えるために必須の栄養素です。しかし食物繊維は消化や排泄までに時間がかかるため、摂り過ぎてしまうと腸内で発酵が盛んになることから、おならの量が増えてしまいます。気になるようでしたら、いったん食物繊維の摂取量を減らして腸内を落ちつかせてから、少しずつまた食物繊維を増やしていくようにすると良いでしょう。
炭酸飲料
炭酸飲料を飲むと、飲料に溶けている炭酸が二酸化炭素と水に分解されます。二酸化炭素は血中に吸収されやすい気体ですが、量が多いと吸収しきれずおならの量も増えることがあります。
喫煙
炭酸飲料を飲むと、飲料に溶けている炭酸が二酸化炭素と水に分解されます。二酸化炭素は血中に吸収されやすい気体ですが、量が多いと吸収しきれずおならの量も増えることがあります。
ストレスや睡眠不足による
自律神経の乱れ
強いストレスがかかると自律神経のバランスが乱れます。その場合、交感神経優位となりやすく、副交感神経の働きが弱まることによって胃腸の働きが低下します。すると、食物の腸内滞留時間が長くなり、おならの量が増え、においもきつくなる傾向があります。
そのことがさらにストレスを招き悪循環になりやすいため、ストレスをうまく逃がしてあげる行動をするようにしましょう。
おならを伴う病気
慢性胃炎
胃に慢性的な炎症が起こっている状態で、原因の8割はピロリ菌感染によるものです。急性胃炎より症状は軽めのことが多いのですが、胃痛、げっぷ、胸やけ、吐き気といった症状に加えておならも増える傾向があります。放置しておくと、胃粘膜が変化して胃がんのリスクが高まります。
過敏性腸症候群
続く腹痛に加えて、便秘、下痢、便秘と下痢の繰り返しなどの便通異常が有り、検査をしても腸に炎症や潰瘍、腫瘍といった器質的な病変がみられないことが特徴の病気です。腸の運動機能や知覚機能がストレスや不安、生活習慣や気候・環境などの問題で障害されるのが原因とされています。中でも異常にガスが溜まってしまうタイプの症状があり、おならが止まらずに人前に出ることができなくなるケースもあります。
大腸がん
大腸がんは、早期の自覚症状がほとんどありません。しかし、進行してくると腫瘍によって腸管に狭窄が起こり、便が通過しにくくなり便秘となることがあります。急に便が細くなる、便秘が続いた後下痢となるなどの症状があらわれますが、便秘によっておならが増えることもあります。
おならの予防
便秘予防のための生活習慣
便秘によって便が腸に滞在する時間が長くなることで、おならが増えたり、腐敗しやすくなって悪臭のあるおならになったりします。つまり便秘を解消・予防することはおならのにおいと量を減らすことに繋がるわけです。
- 便意やおならを我慢しないようにする
- 水分をしっかりと摂る
- 食物繊維をバランス良く摂る
- 適度な運動を習慣化する
などを心がけることによって、便秘を起こしにくくなります。
運動としてはウォーキングやストレッチ、ゆったりと行うスクワットなどが良いでしょう。
食物繊維を摂りやすい食品としては、イモ類、豆類などが理想的です。それに加えて乳酸菌、酪酸菌などが含まれるヨーグルトなどの発酵食品やオリゴ糖などを積極的に摂ると良いでしょう。特に大豆(きな粉)、納豆、ハチミツ、バナナなどはオリゴ糖を多く含んでいます。
きついにおいの原因と
なる食べ物に注意
 便秘じゃないのにおならが臭くなる場合もあります。獣肉、魚肉、鶏卵等の動物性たんぱく質、ネギ、タマネギ、ニラ、ニンニクなど硫黄分の多い食べ物などを食べると、ウェルシュ菌などの悪玉菌が増え、においのきついおならが増える原因となります。どれも必要な栄養分ではありますが、それだけに偏って摂り過ぎたりしないように、野菜やビフィズス菌を含むヨーグルトなどをバランス良く摂ることが大切です。
便秘じゃないのにおならが臭くなる場合もあります。獣肉、魚肉、鶏卵等の動物性たんぱく質、ネギ、タマネギ、ニラ、ニンニクなど硫黄分の多い食べ物などを食べると、ウェルシュ菌などの悪玉菌が増え、においのきついおならが増える原因となります。どれも必要な栄養分ではありますが、それだけに偏って摂り過ぎたりしないように、野菜やビフィズス菌を含むヨーグルトなどをバランス良く摂ることが大切です。
リフレッシュしてストレス解消
ストレスによって副交感神経の働きが低下することで、胃腸などの消化管の働きが低下します。これによって様々な症状があらわれますが、特に過敏性腸症候群や機能性ディスペプシアといった機能性消化管障害に属する病気は、ストレスなどの心因的な要因が発症に大きくかかわっていることが分かっています。
ストレスは日常生活の中で避けて通ることができないものですが、うまくストレスを発散できるよう、自分なりの解消法を見つけておき、あまりため込み過ぎないようにしましょう。
おならを我慢することは
身体に悪い?
おならを我慢してしまうと、いくつかの点で腸だけではなく身体全体に悪影響を与える可能性があります。
- 腸内にガスが溜まることで、腸が膨れ周辺を圧迫して腹痛を起こすことがある
- 腸の動きを悪化させ、運動機能が低下することで最悪腸閉塞に至ることがある
- 腸内に溜まった腐敗ガスは腸壁から吸収され、血液に混じって全身にまわり、口臭や体臭、肌荒れの原因となることがある
以上のような危険性があるため、おならを我慢することはお勧めできません。
腸内細菌叢が整っている正常なおならはさほど多くはなく、においもありません。腸内環境を整えることを気遣い、においの無いおならを気持よく出せるように気をつけましょう。