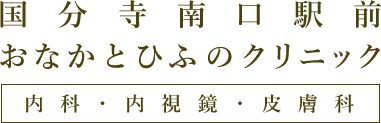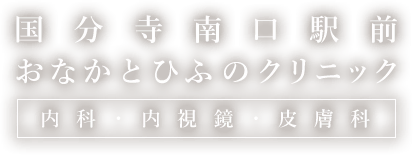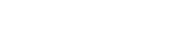胃がもたれる
胃もたれは、一般的な胃の不調による症状の一つで、食物が胃で溶かされるまでに、いつもより時間がかかってしまっている状態を指し、食生活や何らかの病気などによって起こるものです。
主な症状として「食べたものがいつまでも胃に残っている」「胃が重く気分が悪い」などがあります。
胃のもたれとは
 胃は、食べたものを強い酸性の胃酸や消化酵素が混じった胃液でドロドロに溶かし、腸で栄養を吸収しやすくする働きをしています。口から摂り入れた食物は、食道を通り胃に近づくと下部食道括約筋が緩み、胃の入り口にある噴門が開くことで胃に食物を送り込みます。この時、同時に胃の上部が適応性弛緩によって膨らみ、しばらく食物を溜めておけるようにしています。胃の中で食物が溶かされたら、胃の下部が収縮し食物を十二指腸へと送り出します。これを胃排出能と言います。
胃は、食べたものを強い酸性の胃酸や消化酵素が混じった胃液でドロドロに溶かし、腸で栄養を吸収しやすくする働きをしています。口から摂り入れた食物は、食道を通り胃に近づくと下部食道括約筋が緩み、胃の入り口にある噴門が開くことで胃に食物を送り込みます。この時、同時に胃の上部が適応性弛緩によって膨らみ、しばらく食物を溜めておけるようにしています。胃の中で食物が溶かされたら、胃の下部が収縮し食物を十二指腸へと送り出します。これを胃排出能と言います。
この仕組みに何らかの障害が起こると、食べ物がいつまでも胃に滞留し、胃もたれを起こします。その要因としては、食生活の問題、胃粘膜の炎症などの器質的障害、内分泌障害、ストレスなどによる運動機能や知覚機能の障害、加齢による筋力や神経伝達能力の低下などが考えられます。
胃粘膜とは?
胃粘膜は、胃液によって自らが溶けてしまわないよう、円柱上皮という特殊な構造をしており、粘液を出して胃液から守っています。
この機能は、胃への血流がしっかりと確保されることによって、粘液の材料が補給され保たれているのです。
胃もたれの原因
暴飲暴食、加齢やストレスなど
胃もたれは、胃の働きが弱くなって、胃に入った食物がなかなか消化されずに滞留することで起こる症状です。その原因として、何らかの病気から起こるものもありますが、暴飲暴食や加齢によるもの、ストレスなどの精神的問題といった病気以外のもの、妊娠の影響などがあります。
食ベ過ぎ
胃は口から入ってきた食べ物を、適応性弛緩によってしばらくの間は貯蓄します。その間に、胃液によって食物をドロドロに溶かし、栄養吸収をしやすい形にする働きをしています。食べる量が多すぎると、食物を溶かすための時間がかかり、胃もたれを感じるようになります。
また、脂っこいものなどを食べすぎることでも、胃液によって食物を溶かすまでに時間がかかり、胃もたれが生じることがあります。
飲み過ぎ
アルコールは、適量であれば血流を良くしたり、緊張をほぐしたりといった働きがありますが、飲み過ぎることで胃粘膜の働きを低下させることや、腸の働きを弱めて下痢の原因となることもあります。また、アルコールは胃や小腸で吸収され肝臓で分解されますが、飲み過ぎることによって分解に時間がかかると、アルコールの分解過程で生じるアセトアルデヒドの毒性が悪影響を及ぼします。そのため、二日酔いや胃もたれを生じるだけではなく、がん発症のリスクを高めてしまうこともあります。
加齢による胃の働きの低下
胃などの消化管は、常に蠕動運動を繰り返し、消化、排泄するために肛門へと食べたものを送っています。胃は、それと同時に蠕動運動によって食べたものをかき混ぜ、胃液によって食物が溶けやすくなるように働いています。消化が終わると胃の下部が収縮し、蠕動運動を助けながら十二指腸へと食物は移動することになります。
この蠕動運動の機能が加齢などによって低下すると、胃もたれが生じやすくなります。また、加齢によって血流が低下すると胃粘膜の保護機能が低下し、胃もたれなどの不調があらわれやすくなります。
ストレスも胃の働きに影響
胃の働きをコントロールする自律神経がストレスや過労によって乱れてしまうと、蠕動運動などが低下することで正常な胃の動きができなくなり、胃もたれなどがあらわれやすくなります。
妊娠などの影響
妊娠初期には、身体的・精神的な変化によって、悪阻(つわり)を生じるようになります。その症状のあらわれ方には個人差がありますが、胃もたれ、吐き気などは代表的な症状の1つです。さらに、胎児が成長してくると子宮が大きくなって他の臓器を圧迫するため、胃や腸の不調を訴える方も多いです。
胃がもたれる食事
 脂っこい食べ物、味付けの濃い食べ物、唐辛子など激辛の食べ物などの他、熱すぎる食べ物、冷たすぎる食べ物なども胃に負担がかかり、胃もたれを起こすことがあります。その他、コーヒー、紅茶、煎茶などに多く含まれるカフェインも消化に負担をかける原因となりますので、それぞれ適量を守るようにしましょう。
脂っこい食べ物、味付けの濃い食べ物、唐辛子など激辛の食べ物などの他、熱すぎる食べ物、冷たすぎる食べ物なども胃に負担がかかり、胃もたれを起こすことがあります。その他、コーヒー、紅茶、煎茶などに多く含まれるカフェインも消化に負担をかける原因となりますので、それぞれ適量を守るようにしましょう。
胃もたれの症状
胃の不調の感じ方は人それぞれですが、多くあるのは「胃で消化ができずにずっと何か残っている感じ」「胃が重く感じる」「胃がムカムカして夜中に目覚めてしまう」「おなかが減ってこない」などです。
「胃もたれ」と「胸やけ」は混同しやすい症状ですが少し異なります。胃もたれは、胃全体になんとなく不快感が続く症状で、胸やけはみぞおちから喉にかけて熱く灼けるような感覚が一時的に起こる症状です。
胃もたれは胃の消化機能の低下によるもので、胸やけは胃の内容物が食道への逆流し炎症を起こすことが原因となっています。
胃もたれを起こす病気
胃もたれは食事や生活習慣によっても起こりますが、食道、胃、十二指腸などの病気によっても起こります。
胃もたれの代表的な病気は、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、機能性ディスペプシア、ピロリ菌感染、胃がんなどがあります。
これらの中でもピロリ菌感染は、例に挙げたような全ての病気の原因になることが知られています。
ピロリ菌感染が引き起こす病気で最も重篤なものは胃がんです。胃がんは、いまだに多いがんの1つです。そのため、治療法なども研究が進んでおり、早期に発見すれば簡単な治療で完治できます。しかし、早期にはほとんど自覚症状が無く、進行してある程度胃の不調があらわれてから発見されることが多いため、検査などを受けて慎重に治療を行う必要があります。
その一方で、近年増えてきているのは機能性ディスペプシアです。胃などの上部消化管にはっきりした病変が無く、胃の運動機能や知覚機能の障害、その他様々な要因によって起こると考えられている病気です。
胃もたれなどの不快な症状があり、お薬で軽減はしますが再発も多いため、長期的に治療を続けて行くことが大切です。
胃もたれの検査
胃カメラ検査
 胃もたれの原因は、生活習慣から来るようなあまり心配のないものから、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんといった重篤な病気によるものまで様々です。また、器質的な病気が無いからと言って、機能性ディスペプシアなどの機能性胃腸疾患があると、命の危険がなくても日常生活に大きな影響が出てくることもあります。
胃もたれの原因は、生活習慣から来るようなあまり心配のないものから、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんといった重篤な病気によるものまで様々です。また、器質的な病気が無いからと言って、機能性ディスペプシアなどの機能性胃腸疾患があると、命の危険がなくても日常生活に大きな影響が出てくることもあります。
ただの単純な胃もたれなのか、何らかの病気によって起こっているものなのかをはっきりとさせるためにも、胃カメラ検査は重要です。
以前は辛くて苦しいと言われていた胃カメラ検査ですが、当院では様々な工夫をこらし、患者様の苦痛を最低減に抑えることができますので安心してご相談ください。
胃もたれの改善(胃もたれを楽にする方法)
胃にやさしい食べ物
しっかりと煮たうどんや水気の多い麺類、やわらかめのご飯、脂身の少ない食材、油を使わない調理法などで、消化に良い食物を摂るようにしましょう。野菜類や五穀などは身体に良いイメージもありますが、食物繊維が多すぎると消化に負担がかかり、弱った胃の負担になる可能性もあります。まずはご自身の体調と相談しながら、柔らかく吸収の良いものを食べるようにしましょう。
胃もたれを和らげる姿勢
 寝るときや横になって休息する時の姿勢も大切です。
寝るときや横になって休息する時の姿勢も大切です。
中でも、横になる姿勢は大切で、横になる時に頭が胃の位置よりも下がっていることで、胸やけや胃もたれがあらわれやすくなります。それを防ぐためにも、枕を高めにする、上半身を持ち上げ気味にする、などご自身の楽な姿勢を見つけ、マットレスや抱き枕などで調整できるようにしましょう。