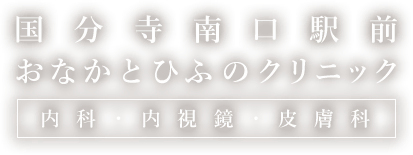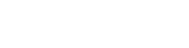食欲不振とは
 食欲という「物を食べたい」という欲求は人間が生きていくために自然に備わっている欲望の1つです。何かを食べて蓄えたエネルギーを、身体活動によって消費した時に血糖値が下がります。そして、それを補おうとして、身体に蓄えられた脂肪を燃焼させエネルギーを作りだします。この燃焼によってできた物質が血中に増加してくると、脳はそれを察知し視床下部にある摂食中枢へ働き、空腹を感じる仕組みになっています。
食欲という「物を食べたい」という欲求は人間が生きていくために自然に備わっている欲望の1つです。何かを食べて蓄えたエネルギーを、身体活動によって消費した時に血糖値が下がります。そして、それを補おうとして、身体に蓄えられた脂肪を燃焼させエネルギーを作りだします。この燃焼によってできた物質が血中に増加してくると、脳はそれを察知し視床下部にある摂食中枢へ働き、空腹を感じる仕組みになっています。
食欲不振というのは、その摂食中枢が何らかの原因によってうまく働かず、「おなかが空いた」という指令が出なくなってしまった状態のことです。疲労や心理状態などによる一時的な現象としては良くあります。
しかし、その状態が長く続くと、身体に必要な栄養素が上手く摂れなくなるため、心身に悪影響を与える悪循環となってしまいます。食欲不振の状態が長く続く時は、身体や心に何らかの病気が生じていることも考えられます。その場合は一度当院までご相談ください。
食欲不振の原因
食欲不振を生じる原因としては、食道から胃、十二指腸、小腸、大腸と続く消化管に加え、肝臓、膵臓、胆嚢などの消化器の病気が最も多いです。その他にも、心不全、慢性腎臓病、甲状腺疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、うつ病や認知症など消化器以外の臓器の病気も考えられます。
消化器の病気として、急性・慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、肝炎や膵炎といったものから、胃がんや肝臓がんなどの消化器がんといったものまで広範囲に渡ります。また、抗菌薬、抗炎症薬、向精神薬、抗がん剤、強心剤といった、病気で服用しているお薬による影響もあります。
さらに、夏バテや過労などの環境によるものや加齢によるものなどの他にも、虫歯や歯周病、口内炎、義歯が合わないなどといった口腔衛生上の問題から起こることもあります。
食欲不振の症状
食欲不振は、空腹感を覚えない、食べたいという欲求が無いという症状ですが、その症状の原因となるものは、病気によって異なります。
一般的に、胃、食道、十二指腸の上部消化管の病気の場合は、胃もたれ、胃痛、胸やけ、げっぷ、吐き気・嘔吐、早期飽満感(食べ始めてすぐおなかがいっぱいになってしまう)といった症状が共通しており、小腸や大腸の下部消化管の病気の場合は、腹痛、腹部膨満感、おなかの張り、下痢、便秘、または下痢と便秘の繰り返しなどの共通した症状があります。なんらかの病気で、上部消化管や下部消化管がダメージを受けている場合、これらの症状が食欲不振を引き起こしていたり、助長していたりすることも考えられます。
一方、脳と消化管の情報伝達の障害によって、食欲不振が起こっている可能性もあります。脳と消化管の間を自律神経がコントロールしており、自律神経が乱れることによって食欲不振が起こることもあります。中でも、ストレスや過労などが続くと、交感神経が優位となって、消化吸収を促進する副交感神経が抑えられるため、食欲不振が助長されることがあります。
食欲不振の検査方法
食欲不振の原因は、前述の通り非常に幅広いです。
そのため、まずは問診を丁寧に行い、考えられる原因を絞り混んでから、その原因に合わせた適切な検査を行っていきます。
問診
問診のポイント
 問診では、食欲不振がいつ頃からどの程度の期間続いているか、食欲不振に伴う症状はどのようなものがあるのか、味覚に変化がおこっていないか、体重減少がないか、服用中のお薬や治療中の病気はないか、生活の大きな変化やストレス要因がないかなど、幅広く確認をします。また、女性の場合は、妊娠の可能性や月経についてお訊ねすることもあります。
問診では、食欲不振がいつ頃からどの程度の期間続いているか、食欲不振に伴う症状はどのようなものがあるのか、味覚に変化がおこっていないか、体重減少がないか、服用中のお薬や治療中の病気はないか、生活の大きな変化やストレス要因がないかなど、幅広く確認をします。また、女性の場合は、妊娠の可能性や月経についてお訊ねすることもあります。
これらの問診の結果を総合した上で、まずは血液検査と尿検査を行い、消化器や腎臓などに炎症や感染がないか、貧血がないかなどを総合的に調べます。また、必要に応じて各種腫瘍マーカーなどの検査も行います。
さらに精密な検査が必要な場合は、画像検査や超音波検査などを行うこともあります。
食欲不振の治療方法
食欲不振の治療は、その原因によって大きく異なります。まずは原因となる病気を特定し、その病気に対する治療をしっかりと行うことが大切です。
特に、重篤な病気でない場合は、薬物療法を基本として行います。
ウイルス感染による急性胃腸炎などの場合には、適切な抗ウイルス薬が無いため、症状に応じて対症療法としてお薬を処方していくことになります。使用するお薬としては、整腸剤や嘔吐が激しい場合には制吐薬を使用し、下痢や嘔吐で脱水の危険がある場合には、点滴療法を行うこともあります。
一方、潰瘍や腫瘍を伴う病気が考えられる場合には、胃カメラ検査や大腸カメラ検査を行うと同時に、出血があれば止血し、ポリープなどは切除するといった処置を行うこともあります。また、潰瘍の場合は、粘膜を現状よりも傷つけないようにするために、胃酸分泌抑制薬や、傷ついた胃や十二指腸粘膜を修復・保護するお薬などを使って薬物療法を行うことになります。
近年注目されている非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による胃炎や胃潰瘍などの場合には、主治医に相談の上で休薬やお薬の変更などを検討しています。
生活習慣の改善
また、食欲不振の原因が生活習慣や食習慣、心因的な問題などにある場合は、以下のような生活習慣の改善が有効になります。
- 毎日決まった時間に3食を摂る
- 寝る時間、起きる時間を一定にするなど規則正しい生活を心がける
- ストレスを適度に発散させる自分なりの方法を作る
- 暴飲暴食、お酒の飲み過ぎなどを控え、肝臓に負担をかけすぎないようにする
- 適度な運動習慣をつける
当院では、改善のための指導なども積極的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。